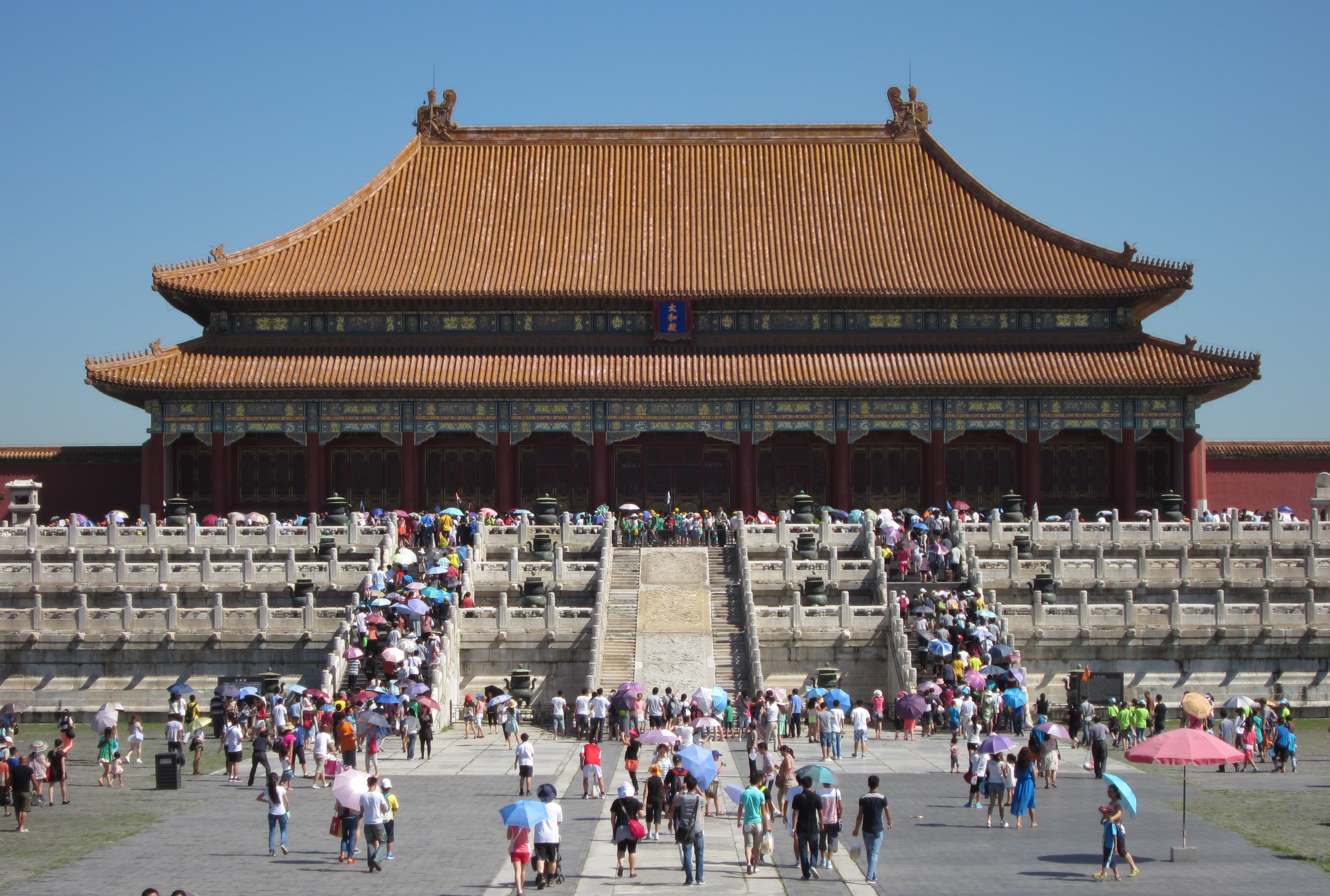[はしがき] 異宗教・多民族世界の混沌―その歴史と現在
[はしがき]
異宗教・多民族世界の混沌―その歴史と現在
鹿毛敏夫
世界は、様々な宗教を信仰する人々と、多様な民族出自を有する人々であふれている。地球上に存在するこの異宗教と多民族は、過去において、時に激しく対立し、また交流と融合を繰り返しながら、現代までの歴史を紡いできた。この共同論集では、そうした宗教と民族の対立・交流の歴史およびその現在を相対的に検証・評価し、二十一世紀のグローバル化した世界における宗教と民族の共存のあり方を考究したい。
その目的のために、私たちは「宗教と民族の対立・交流の現代歴史学的研究」をテーマとする共同研究グループを、二〇一七年に立ち上げた。四年間の研究計画を定め、具体的には、地球上に存在する異宗教と多民族を原因とした対立と交流の歴史とその現在を、日本・アジア・ヨーロッパの三地域に分けて相対的に検証・評価することとした。
ただし、異宗教と多民族の対立・交流・融合の分析と考察は、多様な分野から多角的な視野のもとで行う必要があるため、歴史学・文学・社会学・文化人類学・言語学・地域学・宗教学等の各専門研究者による各々の個別分野研究での分析手法を融合させる手法をとった。専門分野の異なるメンバーによる学際的研究会や講演会を毎年開催するとともに、日本国内では名古屋(愛知県)や岡谷(長野県)、海外ではミャンマーやオーストリアの考察対象地を選定して共同学際調査を実施し、現地で異なる学問領域それぞれの研究手法を実践し、その手法を批判し合いながら、人文社会学の総体としての成果の掲出を心がけた。この手法は、当初描いていた以上の相乗効果があったと思われる。例えば、二〇一八年に実施したミャンマー学際調査では、多民族国家における少数民族の活動家への社会学的インタビュー調査に、文学・歴史学・文化人類学の研究者も参加して意見交換するとともに、十六世紀の南蛮貿易や十七世紀の朱印船貿易で日本にもたらされた伝統的マルタバン壺窯跡の歴史調査にも、社会学・文学・文化人類学の研究者が同行するなどして、事象の多角的視野からの複眼的考察に努め、また、人文社会学の多様な研究手法を融合することで見えてくる新しい世界観について現地で議論を深めることもできた。
その目的のために、私たちは「宗教と民族の対立・交流の現代歴史学的研究」をテーマとする共同研究グループを、二〇一七年に立ち上げた。四年間の研究計画を定め、具体的には、地球上に存在する異宗教と多民族を原因とした対立と交流の歴史とその現在を、日本・アジア・ヨーロッパの三地域に分けて相対的に検証・評価することとした。
ただし、異宗教と多民族の対立・交流・融合の分析と考察は、多様な分野から多角的な視野のもとで行う必要があるため、歴史学・文学・社会学・文化人類学・言語学・地域学・宗教学等の各専門研究者による各々の個別分野研究での分析手法を融合させる手法をとった。専門分野の異なるメンバーによる学際的研究会や講演会を毎年開催するとともに、日本国内では名古屋(愛知県)や岡谷(長野県)、海外ではミャンマーやオーストリアの考察対象地を選定して共同学際調査を実施し、現地で異なる学問領域それぞれの研究手法を実践し、その手法を批判し合いながら、人文社会学の総体としての成果の掲出を心がけた。この手法は、当初描いていた以上の相乗効果があったと思われる。例えば、二〇一八年に実施したミャンマー学際調査では、多民族国家における少数民族の活動家への社会学的インタビュー調査に、文学・歴史学・文化人類学の研究者も参加して意見交換するとともに、十六世紀の南蛮貿易や十七世紀の朱印船貿易で日本にもたらされた伝統的マルタバン壺窯跡の歴史調査にも、社会学・文学・文化人類学の研究者が同行するなどして、事象の多角的視野からの複眼的考察に努め、また、人文社会学の多様な研究手法を融合することで見えてくる新しい世界観について現地で議論を深めることもできた。
その成果としての本書は、以下の構成として編むこととした。
まず第1部「流動する民族社会」では、歴史学・文学・社会学から見た「民族」の移動と越境・交流の実態、そしてその現代的共生の課題について考えたい。
「鎌倉北条氏と南宋禅林―渡海僧無象静照をめぐる人びと」(村井章介)では、鎌倉時代の十三~十四世紀初頭の日本禅宗黎明期に、十九歳の若年で入宋して中国の高僧に随侍し、帰国後に時の政権北条時頼と関わった無象静照という僧侶に着目し、従来ほとんど言及されていないその事蹟を詳細に跡づけるとともに、その時代に日本―中国間を往来した「渡海僧」「渡来僧」と鎌倉武家政権の関係を考察する。
次に、「ドイツ語圏越境作家における言語、民族、文化をめぐって」(土屋勝彦)では、ヨーロッパにおけるユダヤ系ロシア人移民作家や東欧出身移民作家、トルコ人作家等、ドイツ語圏移民作家たちの民族性とその意識について、「越境」する文学という観点から考える。
このようなアジアとヨーロッパの東西における人の移動と民族の越境・交流の歴史は、近現代には一段と活発化し、都市の国際化を進展させた。「近代名古屋にとっての中東―実業界との関係を中心に」(吉田達矢)では、日本におけるそうした国際都市の一例としての名古屋に着目し、特に、明治から昭和中期にかけての名古屋の実業界と中東の関係について分析する。
そして「民族をめぐる対立と交流の位相―滞日ビルマ系難民の国際移動の事例から」(人見泰弘)では、滞日ビルマ系難民の本国離脱から日本滞在、そしてこの十年ほどで見られ始めた本国への帰国に至る過程を通じて、民族をめぐる対立と交流がいかに顕在化するのかを捉え、第1部の展望とする。
まず第1部「流動する民族社会」では、歴史学・文学・社会学から見た「民族」の移動と越境・交流の実態、そしてその現代的共生の課題について考えたい。
「鎌倉北条氏と南宋禅林―渡海僧無象静照をめぐる人びと」(村井章介)では、鎌倉時代の十三~十四世紀初頭の日本禅宗黎明期に、十九歳の若年で入宋して中国の高僧に随侍し、帰国後に時の政権北条時頼と関わった無象静照という僧侶に着目し、従来ほとんど言及されていないその事蹟を詳細に跡づけるとともに、その時代に日本―中国間を往来した「渡海僧」「渡来僧」と鎌倉武家政権の関係を考察する。
次に、「ドイツ語圏越境作家における言語、民族、文化をめぐって」(土屋勝彦)では、ヨーロッパにおけるユダヤ系ロシア人移民作家や東欧出身移民作家、トルコ人作家等、ドイツ語圏移民作家たちの民族性とその意識について、「越境」する文学という観点から考える。
このようなアジアとヨーロッパの東西における人の移動と民族の越境・交流の歴史は、近現代には一段と活発化し、都市の国際化を進展させた。「近代名古屋にとっての中東―実業界との関係を中心に」(吉田達矢)では、日本におけるそうした国際都市の一例としての名古屋に着目し、特に、明治から昭和中期にかけての名古屋の実業界と中東の関係について分析する。
そして「民族をめぐる対立と交流の位相―滞日ビルマ系難民の国際移動の事例から」(人見泰弘)では、滞日ビルマ系難民の本国離脱から日本滞在、そしてこの十年ほどで見られ始めた本国への帰国に至る過程を通じて、民族をめぐる対立と交流がいかに顕在化するのかを捉え、第1部の展望とする。
続く第2部「宗教の断絶と叡智」では、社会学や文化人類学、宗教学等の観点から、「宗教」の融合と衝突・断絶の歴史、および「宗教文化」の多様性・多元性理解に基づく共存への叡智について考える。
宗教の受容と対立の問題は、現代に至る日本の文化に様々な影響を及ぼしてきた。「ボーダレス化する世界と日本の宗教文化」(井上順孝)では、特に二十世紀末からのグローバル化と情報化の加速度的進行がもたらした日本の宗教文化の変容に着目し、ボーダレス化時代における宗教の多様性への柔軟的思考について宗教社会学の観点から考察する。
一方、宗教の断絶と融和の実態解明については、個別地域における文化人類学的観点からの考察も有効である。「ラダックのアイデンティティ運動―もうひとつの「カシミール問題」」(宮坂清)では、インド北部のラダック地方におけるチベット仏教徒による宗教ナショナリズムを取りあげ、十九世紀から現代にかけてのムスリムとの衝突と融和、および近年のヒンドゥー・ナショナリズムの伸張について論じる。
また「インドネシア・アチェ州のイスラーム刑法と人権」(佐伯奈津子)では、東南アジアで最初にイスラームを受容したインドネシア西部のアチェ州をフィールドに、現代イスラーム法による鞭打ち刑やキリスト教会閉鎖等、少数者への不寛容・排外主義の実態を明らかにする。
そして、最終の「宗教と平和―宗教多元社会における戦争」(黒柳志仁)では、宗教学、特に旧約聖書学の観点から、宗教と戦争・政治の問題を取りあげる。ユダヤ教、キリスト教、イスラーム等の一神教がもつ信仰と教義の相違や、ヨーロッパ社会における政治と宗教の関係、および宗教多元社会における閉鎖性の問題を検討して、第2部のまとめとする。
宗教の受容と対立の問題は、現代に至る日本の文化に様々な影響を及ぼしてきた。「ボーダレス化する世界と日本の宗教文化」(井上順孝)では、特に二十世紀末からのグローバル化と情報化の加速度的進行がもたらした日本の宗教文化の変容に着目し、ボーダレス化時代における宗教の多様性への柔軟的思考について宗教社会学の観点から考察する。
一方、宗教の断絶と融和の実態解明については、個別地域における文化人類学的観点からの考察も有効である。「ラダックのアイデンティティ運動―もうひとつの「カシミール問題」」(宮坂清)では、インド北部のラダック地方におけるチベット仏教徒による宗教ナショナリズムを取りあげ、十九世紀から現代にかけてのムスリムとの衝突と融和、および近年のヒンドゥー・ナショナリズムの伸張について論じる。
また「インドネシア・アチェ州のイスラーム刑法と人権」(佐伯奈津子)では、東南アジアで最初にイスラームを受容したインドネシア西部のアチェ州をフィールドに、現代イスラーム法による鞭打ち刑やキリスト教会閉鎖等、少数者への不寛容・排外主義の実態を明らかにする。
そして、最終の「宗教と平和―宗教多元社会における戦争」(黒柳志仁)では、宗教学、特に旧約聖書学の観点から、宗教と戦争・政治の問題を取りあげる。ユダヤ教、キリスト教、イスラーム等の一神教がもつ信仰と教義の相違や、ヨーロッパ社会における政治と宗教の関係、および宗教多元社会における閉鎖性の問題を検討して、第2部のまとめとする。
第3部「個の相克と相対化される「国家」」においては、前部までで明らかにしてきた地球上の異宗教と多民族の対立・交流・融合の根源にある、個々の人間の想いとその相克、さらにそこから相対化される「国家」意識の具体的深層について、各分野から検討する。
「戦国大名の「国」意識と「地域国家」外交権」 (鹿毛敏夫)では、有史以来、中華世界の周辺国の一つとして中国皇帝から「日本国王」に冊封されることで維持してきた日本の国家外交が、十六世紀半ば以降に「国」意識を成熟させた戦国大名による「地域国家」 外交権の行使によって、 脱中華志向へと性質転化していった実態を歴史学的に明らかにする。
また「日本中世の「暴力」と現代の「教育」」(メイヨー・クリストファー)では、日本とヨーロッパ社会における中世的刑罰、特に身体刑の存在に着目し、暴力への耐性の高い社会と国家の特徴およびその意味について、歴史的に考察する。
一方、「一亡命作家の軌跡:西欧キリスト教世界の対岸から―フアン・ゴイティソーロのバルセロナ、サラエヴォ、マラケシュ」(今福龍太)では、二〇一七年にマラケシュで没したスペインの亡命作家フアン・ゴイティソーロを題材に、西欧キリスト教世界の非寛容からの決別とイスラーム民衆世界への浸透の軌跡について論じる。
そして、最後の「保育園で働く看護師の語りから考える多文化共生」(梶原彩子)では、現代日本総人口の約二パーセントに上り増加の一途をたどる在住外国人を念頭に、保育園現場看護師の「語り」(ライフストーリー・インタビュー)から、コミュニケーション・生活支援の課題、および多文化共生の地域づくりに向けた問題点についてまとめる。
『日本宗教史』全六巻 (吉川弘文館、二〇二〇~二一年)の刊行等、宗教と民族のあり方を模索する研究は、活発かつ重厚な研究史をもつが、本書が目指すような、多分野の研究者による異なる分析手法を駆使した考察を融合させて整理しようとする書物は、意外に多くない。同一学問分野の研究者が集った共同研究とその成果論集は、確かに研究対象を深く掘り下げて考察する奥深さがあるものの、一方で、研究のベクトルが同一のため予定調和的な結論になりがちである。宗教と民族の課題は、多種多様な広がりをもつことに最大の特徴があり、例えば、実証主義の歴史学では分析できない事象が、人間の心象に切り込む文学からの分析によって、容易に課題解決できることがある。読者には、地球上の「異宗教」と「多民族」が織りなす混沌の世界をむしろ堪能しつつ、そこから生じる課題に多様な角度から切り込んでいく人文学の諸学問分野の特徴も感じ取りながら、各論考を読み進めていただきたい。
「戦国大名の「国」意識と「地域国家」外交権」 (鹿毛敏夫)では、有史以来、中華世界の周辺国の一つとして中国皇帝から「日本国王」に冊封されることで維持してきた日本の国家外交が、十六世紀半ば以降に「国」意識を成熟させた戦国大名による「地域国家」 外交権の行使によって、 脱中華志向へと性質転化していった実態を歴史学的に明らかにする。
また「日本中世の「暴力」と現代の「教育」」(メイヨー・クリストファー)では、日本とヨーロッパ社会における中世的刑罰、特に身体刑の存在に着目し、暴力への耐性の高い社会と国家の特徴およびその意味について、歴史的に考察する。
一方、「一亡命作家の軌跡:西欧キリスト教世界の対岸から―フアン・ゴイティソーロのバルセロナ、サラエヴォ、マラケシュ」(今福龍太)では、二〇一七年にマラケシュで没したスペインの亡命作家フアン・ゴイティソーロを題材に、西欧キリスト教世界の非寛容からの決別とイスラーム民衆世界への浸透の軌跡について論じる。
そして、最後の「保育園で働く看護師の語りから考える多文化共生」(梶原彩子)では、現代日本総人口の約二パーセントに上り増加の一途をたどる在住外国人を念頭に、保育園現場看護師の「語り」(ライフストーリー・インタビュー)から、コミュニケーション・生活支援の課題、および多文化共生の地域づくりに向けた問題点についてまとめる。
『日本宗教史』全六巻 (吉川弘文館、二〇二〇~二一年)の刊行等、宗教と民族のあり方を模索する研究は、活発かつ重厚な研究史をもつが、本書が目指すような、多分野の研究者による異なる分析手法を駆使した考察を融合させて整理しようとする書物は、意外に多くない。同一学問分野の研究者が集った共同研究とその成果論集は、確かに研究対象を深く掘り下げて考察する奥深さがあるものの、一方で、研究のベクトルが同一のため予定調和的な結論になりがちである。宗教と民族の課題は、多種多様な広がりをもつことに最大の特徴があり、例えば、実証主義の歴史学では分析できない事象が、人間の心象に切り込む文学からの分析によって、容易に課題解決できることがある。読者には、地球上の「異宗教」と「多民族」が織りなす混沌の世界をむしろ堪能しつつ、そこから生じる課題に多様な角度から切り込んでいく人文学の諸学問分野の特徴も感じ取りながら、各論考を読み進めていただきたい。