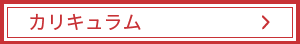経営政策専攻 博士後期課程
より高度な研究を行い、最高学位「博士号」の授与をめざします
博士後期課程は、自律的な研究能力と豊かな学識を身につけたい意欲的な人を受け入れています。最高の学位である博士号が授与されることは、単に学識を証明するだけでなく、博士(Ph.D.;Doctor of Philosophy)にふさわしい人格の所有者であることが求められることから、博士課程は全人教育であるといえます。
博士論文とは、研究の成果を論文にまとめたものです。研究とは、新しい分野やテーマについて検証分析することで新事実を発見し、それを論理的に構築して結論を導き出すことです。
研究には、常に斬新性と独創性が求められ、また研究テーマは広く社会や人類に貢献するものであり、かつ研究の成果について有意義性が認められなければなりません。
博士論文とは、研究の成果を論文にまとめたものです。研究とは、新しい分野やテーマについて検証分析することで新事実を発見し、それを論理的に構築して結論を導き出すことです。
研究には、常に斬新性と独創性が求められ、また研究テーマは広く社会や人類に貢献するものであり、かつ研究の成果について有意義性が認められなければなりません。
学位取得までの学修研究計画
入学から学位(博士)取得までの標準的な学修研究計画は次のとおりです。
博士後期課程3年間の主な学修・研究の流れ(モデル)
| 入学試験時 | 研究計画の確認 面接において研究計画書にもとづき、研究の内容を確認する。 |
|
| 1年次 | 博士論文のための研究調査 | |
| 4月 | 指導教員の決定と研究の準備 指導教員は、入学試験の結果をもとに合格通知時に連絡している。指導教員の助言のもと、各院生の研究テーマに沿った履修計画を作成し、「履修登録票」を提出する。また、院生は、論文のテーマ設定、資料の収集、執筆方法等、適時指導教員より指導を受け、論文執筆に向けて準備を進める。 |
|
| 10月 | 研究題目届の提出 | |
| 2年次 | 博士論文執筆 | |
| 9~11月 | 中間発表申請書の提出 指導教員の許可を得た上で、「中間発表申請書」を大学院事務室に提出し、中間発表の準備を進める。 |
|
| 10月 | 学位論文計画書提出 学位論文計画書は、論文提出の6か月前までに、指導教員の許可を得て提出する。学位論文計画書では、論文題目、目次、論文概要、現在の執筆状況を記載する。 |
|
| 12月 | 中間発表 中間発表では、各自の論文の概要や現在の進行状況、今後の調査と執筆の予定について、決められた時間内で概要を発表し、指導教員・副査や他の教員から質問をもらい、テーマをより追及するための手がかりとする。 |
|
| 3年次 | 論文審査 | |
| 5月 | 予備審査 指導教員を主査とし、研究科委員会において選出された教授3名以上により、審査委員が構成され、博士論文の審査がおこなわれる。 |
|
| 9月 | 本審査・最終試験 博士論文が予備審査合格となった後に、学位授与申請書を受け付け、これを研究科委員会が受理した後、本審査(最終試験)を実施する。最終試験は学位論文の内容およびこれと関連する学識と研究能力について審査するものとし、口頭試問および筆答試問によっておこなわれる。 |
|
今までの博士学位授与者
| 学位授与日 | 番号 | 氏名 | 学位論文タイトル |
| 2001年11月30日 | 甲-1 | 太田 国明 | コイルセンター経営のグローバリゼーション -コイルセンターのシステム変革の課題とマーケティングおよび再編の研究- |
| 2001年11月30日 | 甲-2 | 村瀬 伸二 | 中国・郷鎮企業における人的資源政策の改革に関する研究 |
| 2001年11月30日 | 甲-3 | 史 自力 | 中国における外資導入の実態に関する研究 |
| 2002年3月31日 | 甲-4 | 川津 昌作 | 不動産投資における「成長」メカニズムと成長のポジションに関する研究 |
| 2002年3月31日 | 甲-5 | 納富 義宝 | 構造転換期の日本銑鉄鋳物業 ~素形材および地域産業の視点から~ |
| 2004年3月31日 | 甲-6 | 馬上 幸夫 | インドネシアにおける政権と財閥の癒着構造に関する研究 |
| 2005年3月15日 | 甲-7 | 平手 賢治 | 近代的思想枠組としての経営学批判 -「賢慮としての経営学」における基礎理論- |
| 2006年3月15日 | 甲-8 | 林 勇 | 中国社会主義市場経済下における民営商業の復活 -主要都市と東北地方の個人商業の事例を中心に- |
| 2006年3月15日 | 甲-9 | 劉 麗君 | 中国の外貨導入と技術移転の波及効果 -中国遼寧省を中心として- |
| 2007年2月6日 | 甲-10 | 佐久間 清美 | 地域保健とマーケティング |
| 2007年5月30日 | 甲-11 | 藤田 泰正 | 日本工作機械産業論 -マシニングセンタの戦略的意義を踏まえて- |
| 2009年3月16日 | 甲-12 | 中山 孝幸 | 半導体産業にみる発展・衰退・再生のダイナミズム -基本構造分析による支配モデル視点からのアプローチ- |
| 2011年3月16日 | 甲-13 | 池ヶ谷 周治 | 財務報告に係る内部統制整備・評価の研究 |
| 2012年3月15日 | 甲-14 | 塚原 薫 | 医療法人の発展と制度改革の課題 -医業経営における非営利性と営利性のはざまで- |
| 2012年3月15日 | 甲-15 | 朝原 邦夫 | 中小企業における管理会計システム構築の可能性 -経営計画の策定との関連を中心に- |
| 2012年3月15日 | 甲-16 | 程 永帥 | 中国における日系メーカーのニューリーダーシップ論 -「技」「才」「徳」の三位一体化による管理者づくりと経営現地化に向けて- |
| 2012年3月15日 | 甲-17 | 杉山 友城 | 地域活性の理論と方法 |
| 2012年3月15日 | 甲-18 | 古橋 敬一 | 地域創造の視点と実践 -まちづくりの新たな展開をめざして- |
| 2013年3月16日 | 甲-19 | 横井 由美子 | 自治体病院改革と地域連携 -自治体病院の再生と存続をめざして- |
| 2013年9月12日 | 甲-20 | 大野 弘恵 | 助産活動の多様な展開とその活性化に関する研究 -「助産師」の役割と課題の考察にもとづいて- ▶リポジトリへ |
| 2015年3月21日 | 甲-21 | 太田 信義 | 技術領域におけるアウトソーシングの役割と課題 -自動車産業を主体にして- ▶リポジトリへ |
| 2015年6月10日 | 甲-22 | 白 明 | 内モンゴルにおける産業経営と地域発展 -持続可能な複合型経営への日中比較アプローチ- ▶リポジトリへ |
| 2015年6月10日 | 甲-23 | 井手 芳美 | 中国の日系企業にみる創造的経営と人づくり -「経営理念」を活かしたグローバル化の新地平- ▶リポジトリへ |
| 2017年3月21日 | 甲-24 | 宮島 康暢 | 中小企業の発展段階に応じた「経営理念に基づく経営計画」の策定および実行に関する研究 -情報の非対称性緩和の視点から- ▶リポジトリへ |
| 2018年7月4日 | 甲-25 | 金岡 勝一 | 非営利組織の財務的生存力への考察 -介護サービス提供主体の継続性からの視点- ▶リポジトリへ |
| 2018年7月4日 | 甲-26 | 程 永元 | 中国における食の安全・安心システムづくり -法制・行政・現場の三位一体アプローチ- ▶リポジトリへ |
| 2020年3月21日 | 甲-27 | ナンス ナンダァ アウン | ミャンマーの「体制」転換-経済発展戦略の視点から- ▶リポジトリへ |
| 2021年3月20日 | 甲-28 | 藤井 隆久 | 石田退三論-トヨタ自動車の強靭性の原点- ▶リポジトリへ |
| 2023年3月19日 | 甲-29 | グエン ティ クエン | ベトナムにおける「ドイモイ」前後の政策転換と農業経営の変革―21世紀における新たな成長経路を求めて― ▶リポジトリへ |
| 2024年3月20日 | 甲-30 | 程 遠紅 | 中国における都市生活ごみの状況と課題―法治・管理・教育の協働による環境改善のシステムと人材づくり― ▶リポジトリへ |
| 2001年12月25日 | 乙-1 | 河村 幹夫 | 米国商品先物市場の研究 ~CFTCの「規制・自由・拡大」思想~ |
| 2010年3月16日 | 乙-2 | 庵原 孝文 | 日本企業の中国巨大市場への展開 |
| 2019年3月23日 | 乙-3 | 櫻井 善行 | 「企業福祉」の日本的特徴と課題 ▶リポジトリへ |
| 2019年9月17日 | 乙-4 | 冨澤 公子 | 奄美のシマ(集落)にみる文化資本を活かした地域経営 ―長寿と人間発達を支える伝統と協働のダイナミズム― ▶リポジトリへ |
| 2021年9月16日 | 乙-5 | 濱 真理 | 公共政策の合意形成過程 ―廃棄物処理施設立地をめぐる市民・行政・第三者のあり方― ▶リポジトリへ |
| 2024年9月18日 | 乙-6 | 浅沼 宏和 | 現代的な内部統制制度、リスクマネジメント、コーポレートガバナンスー「自己統治・第三者認証型」統治システムへの転換の力学ー ▶リポジトリへ |