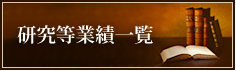総合研究所
2023年度研究助成
課題・共同研究
・陶磁器産地「瀬戸」の将来像と持続可能な展開に関する政策研究【継続】
(本学が関係する地域の課題及び活性化に関する研究) 研究代表者:現代社会学部 小林甲一 この研究は、本学に蓄積された地域政策研究と陶磁器産業研究を融合させることによって瀬戸焼振興による地域活性化という瀬戸市の課題にアプローチし、他産地との比較も視野に入れて陶磁器産地「瀬戸」の将来像を描き、地域で共有することを通して瀬戸における陶磁器産業の持続可能な展開に資する政策のあり方を明らかにする。また、これは、瀬戸市ものづくり商業振興課と連携して政策協働型・「地域伴走」型の政策研究として行うものであり、政策の研究と実践を地域において有機的に協働させることで研究成果をそのまま地域活性化に活かすとともに、地域からのフィードバックによって研究成果の実を高めていき、今後の政策提言にもつなげていく。
・日本におけるキリスト教教育━「敬神愛人」の系譜の探究━【継続】
(キリスト教及び「建学の精神」に関する研究) 研究代表者:国際文化学部 黒柳志仁 本学の建学の精神の「敬神愛人」は、アメリカのキリスト教プロテスタント教会宣教師のF.C.クライン博士の創設による名古屋英和学校より引き継がれて、136年の歴史と伝統を有している。その長い歴史と伝統において、「敬神愛人」の系譜をその5名の代表者(F.C.クライン、メアリー・クライン、U.G.モルフィ、内村鑑三、福田敬太郎)を通して探求していく。これによって、「敬神愛人」がどのように具体的に、多様に展開されて来たかを認識して、日本におけるキリスト教教育において「敬神愛人」が果たしてきた豊かな役割と今後の可能性を探求していく。
・ローカリティ形成における宗教の関与についての学際的比較研究【継続】
(学部及び学科の特色づけに資する研究) 研究代表者:国際文化学部 宮坂 清 ローカリティ(Locality、地域性)が形成される際に、宗教がいかに関与するかについて、日本を含むアジアの事例を比較しつつ考察するのが本研究の目的である。宗教は主要なコンテクストのひとつとして種々のローカリティの形成や変化に関わってきたと考えられるが、それはどのようにしてであるか。この問題を、宗教が関わる事例を各地から収集し、それをコンテクスト的に解釈し、相互に比較するという作業をつうじて明らかにする。
・神経筋電気刺激が人工関節置換術後の筋力および動作能力の改善に与える影響【継続】
(学部及び学科の特色づけに資する研究) 研究代表者:リハビリテーション学部 渡邊晶規 本研究課題の目的は、① 人工膝関節全置換術後早期からの神経筋電気刺激治療が、その後の大腿四頭筋筋力の回復にどのような影響を与えるか明らかにすること、ならびに② 神経筋電気刺激による異なる収縮様式(求心性収縮運動と遠心性収縮運動)の効果に差があるかどうかを明らかにすること、の2点である。
・陶磁器産地「瀬戸」の将来像と持続可能な展開に関する政策研究【継続】
(本学が関係する地域の課題及び活性化に関する研究) 研究代表者:現代社会学部 小林甲一 この研究は、本学に蓄積された地域政策研究と陶磁器産業研究を融合させることによって瀬戸焼振興による地域活性化という瀬戸市の課題にアプローチし、他産地との比較も視野に入れて陶磁器産地「瀬戸」の将来像を描き、地域で共有することを通して瀬戸における陶磁器産業の持続可能な展開に資する政策のあり方を明らかにする。また、これは、瀬戸市ものづくり商業振興課と連携して政策協働型・「地域伴走」型の政策研究として行うものであり、政策の研究と実践を地域において有機的に協働させることで研究成果をそのまま地域活性化に活かすとともに、地域からのフィードバックによって研究成果の実を高めていき、今後の政策提言にもつなげていく。
・日本におけるキリスト教教育━「敬神愛人」の系譜の探究━【継続】
(キリスト教及び「建学の精神」に関する研究) 研究代表者:国際文化学部 黒柳志仁 本学の建学の精神の「敬神愛人」は、アメリカのキリスト教プロテスタント教会宣教師のF.C.クライン博士の創設による名古屋英和学校より引き継がれて、136年の歴史と伝統を有している。その長い歴史と伝統において、「敬神愛人」の系譜をその5名の代表者(F.C.クライン、メアリー・クライン、U.G.モルフィ、内村鑑三、福田敬太郎)を通して探求していく。これによって、「敬神愛人」がどのように具体的に、多様に展開されて来たかを認識して、日本におけるキリスト教教育において「敬神愛人」が果たしてきた豊かな役割と今後の可能性を探求していく。
・ローカリティ形成における宗教の関与についての学際的比較研究【継続】
(学部及び学科の特色づけに資する研究) 研究代表者:国際文化学部 宮坂 清 ローカリティ(Locality、地域性)が形成される際に、宗教がいかに関与するかについて、日本を含むアジアの事例を比較しつつ考察するのが本研究の目的である。宗教は主要なコンテクストのひとつとして種々のローカリティの形成や変化に関わってきたと考えられるが、それはどのようにしてであるか。この問題を、宗教が関わる事例を各地から収集し、それをコンテクスト的に解釈し、相互に比較するという作業をつうじて明らかにする。
・神経筋電気刺激が人工関節置換術後の筋力および動作能力の改善に与える影響【継続】
(学部及び学科の特色づけに資する研究) 研究代表者:リハビリテーション学部 渡邊晶規 本研究課題の目的は、① 人工膝関節全置換術後早期からの神経筋電気刺激治療が、その後の大腿四頭筋筋力の回復にどのような影響を与えるか明らかにすること、ならびに② 神経筋電気刺激による異なる収縮様式(求心性収縮運動と遠心性収縮運動)の効果に差があるかどうかを明らかにすること、の2点である。
課題・個人研究
・イギリスの女性宣教師とレディ・トラベラーの視点:日本における功績と母国での生活
(キリスト教及び「建学の精神」に関する研究) 研究代表者:外国語学部 西村美保 本研究では、19世紀後半から20世紀初頭に日本を含むアジアを旅したイギリスの女性宣教師と旅行者、レディ・トラベラーに焦点を当てる。日本についての著作物を通してその足跡をたどり、西洋的視点や功績、来日前後の様々な事情を明らかにすることを目的とする。
・イギリスの女性宣教師とレディ・トラベラーの視点:日本における功績と母国での生活
(キリスト教及び「建学の精神」に関する研究) 研究代表者:外国語学部 西村美保 本研究では、19世紀後半から20世紀初頭に日本を含むアジアを旅したイギリスの女性宣教師と旅行者、レディ・トラベラーに焦点を当てる。日本についての著作物を通してその足跡をたどり、西洋的視点や功績、来日前後の様々な事情を明らかにすることを目的とする。
一般・共同研究
・スキー実習を中心とした学部教育に資するスノースポーツの社会学的・教育学的・運動学的研究【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 齋藤健治 スポーツ健康学部におけるスキー実習を、貴重なウインター・アウトドア実習として継続するにあたり、アルペンスキーの技術および指導法を学びの中心に据えながらも、スノースポーツ(アルペンスキー、バックカントリースキー、スキーツアーなど)を社会学的、運動学的、教育学的等幅広い視点で捉え直し、スキー実習そのもの、そしてその他のスポーツ科目との接続を強化し、学部教育の質向上の一助としたい。そのための調査,計測による分野横断的な研究を実施する。
・児童生徒の運動に対する効力感の向上を促す運動指導法の検討【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 四方田健二 近年、子どもの体力、運動習慣の二極化の傾向がみられ、学校の体育授業以外で運動する機会の減少が深刻となっている。運動の日常化および卒業後の生涯スポーツの継続のためには運動に対する自己効力感を高めることが重要である。本研究では、児童生徒の運動に対する効力感を向上させるための体育授業等の支援を行い、効力感と運動習慣、運動意欲、体力、運動能力等の実態について明らかにするとともに、効力感の変容過程および効果的な支援や指導の在り方を検討する。
・教師教育カリキュラムの開発 -初任者のリアリティ・ショック緩和ケアプログラムの開発-【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 滝浪常雄 本研究は、初任期(採用1年目から3年目)の小学校教師の経験する教職志望段階に抱く理想と学校現場で直面するギャップ(リアリティ・ショック)や困難の実情を明らかにし、どのように不安や困難を乗り越え教師として成長していくかを検討する。また、これを踏まえ教員養成課程において初任期のギャップへの理解や対処方法に関する指導を取り入れ、養成から採用、現職への移行を支援する方略を検討する。
・ラートおよびGボール運動の初心者に対する指導法の検討【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 堀場みのり 体操運動、中でもラート、Gボールは、日常生活や一般的なスポーツ種目では経験できない腕支持や懸垂、倒立、バランス、回転運動などの多様な運動感覚を含んでおり、誰もが楽しんで実施することのできる運動としての可能性が期待される。とはいえ、初心者への指導法の検討は十分とはいえず、効果的な練習方法や指導の順序などについて知見が蓄積されていないことが課題となっている。本研究では、子ども及び大学生に対するラートおよびGボール運動の指導法を検討し、指導実践を行いその成果を検証する。特に初心者へのラートおよびGボール運動の指導法を提案し、指導経験の少ない指導者に役立てられる知見を得ることを目指す。
・バーチャルリアリティシステムの医療、教育現場への応用【継続】
研究代表者:リハビリテーション学部 佐藤菜穂子 バーチャルリアリティ(virtual reality:VR)技術は近年飛躍的に進歩しており、教育現場や医療現場への応用が進んでいる。本研究ではVR技術の利点である、三次元情報として可視化できる点、ヒトが受ける刺激を操作することができる点を、以下の2つの分野に応用し研究を行う。Ⅰ 教育現場への応用として、ダンスの指導現場におけるパフォーマンスのフィードバックツールとしての応用を検討する。Ⅱ 医療現場への応用として、空間認知能力の低下がある症例の治療に応用し、その効果を検討する。
・スキー実習を中心とした学部教育に資するスノースポーツの社会学的・教育学的・運動学的研究【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 齋藤健治 スポーツ健康学部におけるスキー実習を、貴重なウインター・アウトドア実習として継続するにあたり、アルペンスキーの技術および指導法を学びの中心に据えながらも、スノースポーツ(アルペンスキー、バックカントリースキー、スキーツアーなど)を社会学的、運動学的、教育学的等幅広い視点で捉え直し、スキー実習そのもの、そしてその他のスポーツ科目との接続を強化し、学部教育の質向上の一助としたい。そのための調査,計測による分野横断的な研究を実施する。
・児童生徒の運動に対する効力感の向上を促す運動指導法の検討【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 四方田健二 近年、子どもの体力、運動習慣の二極化の傾向がみられ、学校の体育授業以外で運動する機会の減少が深刻となっている。運動の日常化および卒業後の生涯スポーツの継続のためには運動に対する自己効力感を高めることが重要である。本研究では、児童生徒の運動に対する効力感を向上させるための体育授業等の支援を行い、効力感と運動習慣、運動意欲、体力、運動能力等の実態について明らかにするとともに、効力感の変容過程および効果的な支援や指導の在り方を検討する。
・教師教育カリキュラムの開発 -初任者のリアリティ・ショック緩和ケアプログラムの開発-【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 滝浪常雄 本研究は、初任期(採用1年目から3年目)の小学校教師の経験する教職志望段階に抱く理想と学校現場で直面するギャップ(リアリティ・ショック)や困難の実情を明らかにし、どのように不安や困難を乗り越え教師として成長していくかを検討する。また、これを踏まえ教員養成課程において初任期のギャップへの理解や対処方法に関する指導を取り入れ、養成から採用、現職への移行を支援する方略を検討する。
・ラートおよびGボール運動の初心者に対する指導法の検討【継続】
研究代表者:スポーツ健康学部 堀場みのり 体操運動、中でもラート、Gボールは、日常生活や一般的なスポーツ種目では経験できない腕支持や懸垂、倒立、バランス、回転運動などの多様な運動感覚を含んでおり、誰もが楽しんで実施することのできる運動としての可能性が期待される。とはいえ、初心者への指導法の検討は十分とはいえず、効果的な練習方法や指導の順序などについて知見が蓄積されていないことが課題となっている。本研究では、子ども及び大学生に対するラートおよびGボール運動の指導法を検討し、指導実践を行いその成果を検証する。特に初心者へのラートおよびGボール運動の指導法を提案し、指導経験の少ない指導者に役立てられる知見を得ることを目指す。
・バーチャルリアリティシステムの医療、教育現場への応用【継続】
研究代表者:リハビリテーション学部 佐藤菜穂子 バーチャルリアリティ(virtual reality:VR)技術は近年飛躍的に進歩しており、教育現場や医療現場への応用が進んでいる。本研究ではVR技術の利点である、三次元情報として可視化できる点、ヒトが受ける刺激を操作することができる点を、以下の2つの分野に応用し研究を行う。Ⅰ 教育現場への応用として、ダンスの指導現場におけるパフォーマンスのフィードバックツールとしての応用を検討する。Ⅱ 医療現場への応用として、空間認知能力の低下がある症例の治療に応用し、その効果を検討する。
一般・共同研究
・瞬発的なパフォーマンス発揮が求められるアスリートにおけるコンディション評価法の開発
研究者:スポーツ健康学部 鈴木啓太 アスリートは日々トレーニングを行うことで、高い競技力の獲得を目指す一方で、本人が気づかないうちに、オーバートレーニングを続け、慢性的な疲労状態に陥るアスリートは少なくない。本研究では、近年、瞬発的な競技パフォーマンスとの関連が報告されているIsometric Mid-Thigh Pull(IMTP)に着目し、瞬発的なパフォーマンスが求められるアスリートのコンディション評価法を開発することを目的とする。具体的には、ジャンプやスプリント動作を繰り返す疲労課題を実施して、即自的にIMTPの数値に変化が現れるかを検証する。加えて、強化期における継続的に測定したIMTPの数値をジャンプ回数、スプリント回数といった運動負荷の関係を検証する。
・瞬発的なパフォーマンス発揮が求められるアスリートにおけるコンディション評価法の開発
研究者:スポーツ健康学部 鈴木啓太 アスリートは日々トレーニングを行うことで、高い競技力の獲得を目指す一方で、本人が気づかないうちに、オーバートレーニングを続け、慢性的な疲労状態に陥るアスリートは少なくない。本研究では、近年、瞬発的な競技パフォーマンスとの関連が報告されているIsometric Mid-Thigh Pull(IMTP)に着目し、瞬発的なパフォーマンスが求められるアスリートのコンディション評価法を開発することを目的とする。具体的には、ジャンプやスプリント動作を繰り返す疲労課題を実施して、即自的にIMTPの数値に変化が現れるかを検証する。加えて、強化期における継続的に測定したIMTPの数値をジャンプ回数、スプリント回数といった運動負荷の関係を検証する。
一般・個人研究
・ESG投資におけるキリスト教の役割
研究者:法学部 坂東洋行 日英両国の機関投資家を規律するスチュワードシップ・コードは、投資先企業に対するエンゲージメントを通じたスチュワードシップを求めているが、英国国教会のジャステイン・ウェルビー大司教の「スチュワードシップは、協会の倫理的で責任ある投資行動に適合し、社会と公益に対する広範な責任を反映しかつ支援していく」との発言にある通り、単なる顧客の経済的な利益最大化ではなく、社会全般への責任を指す。本研究では同教会がはたすスチュワードシップを中心に検証し、ESG(環境、社会、ガバナンス)投資における地球温暖化防止等に対するキリスト教の役割を明確にすることによって、スチュワードシップとエンゲージメントの国内の理解を再構築することを目的とする。
・ESG投資におけるキリスト教の役割
研究者:法学部 坂東洋行 日英両国の機関投資家を規律するスチュワードシップ・コードは、投資先企業に対するエンゲージメントを通じたスチュワードシップを求めているが、英国国教会のジャステイン・ウェルビー大司教の「スチュワードシップは、協会の倫理的で責任ある投資行動に適合し、社会と公益に対する広範な責任を反映しかつ支援していく」との発言にある通り、単なる顧客の経済的な利益最大化ではなく、社会全般への責任を指す。本研究では同教会がはたすスチュワードシップを中心に検証し、ESG(環境、社会、ガバナンス)投資における地球温暖化防止等に対するキリスト教の役割を明確にすることによって、スチュワードシップとエンゲージメントの国内の理解を再構築することを目的とする。
研修(教育研究活動)
学部 国際文化学部
氏名 宮坂清
期間 2022年4月1日~2023年3月31日
国 日本
機関 琉球大学国際地域創造学部
研修課題 南西諸島のローカリティ形成における宗教の関与についての研究
研修概要
本研修は、期間前半は主に沖縄の宗教や民俗に関する文献調査を行い、期間後半は対象地域を八重山諸島に絞り現地調査を実施した。この現地調査においては、(1)石垣島の台湾人コミュニティ、(2)石垣島川平などの宗教民俗、(3)移住者たちのスピリチュアリティ、(4)与那国島の共同売店に関する調査を行い、八重山諸島に特有のローカリティの生成を観察することができた。今後も調査を継続したい。
学部 国際文化学部
氏名 佐伯奈津子
期間 2022年4月2日~2023年3月30日
国 インドネシア
機関 アルムスリム大学
研修課題 日系インドネシア人家族の軌跡
研修概要
太平洋戦争後もインドネシアに残留し、インドネシア独立戦争に参加した元日本軍兵士・軍属(残留日本人)が、インドネシア政治や日本との経済関係にどのような影響を与えたか、その家族がどのような暮らしを営んできたか、二世・三世への聞き取りや、互助組織「福祉友の会」での資料収集などを通じて調査した。
学部 スポーツ健康学部
氏名 四方田健二
期間 2022年9月1日~2023年8月4日
国 イギリス
機関 ストラスクライド大学
研修課題 イギリスの体育指導に関わる教員養成および現職教師の支援に関する調査
研修概要
研修中はDavid Kirk教授のもとでスコットランドの学校体育の実態および体育科の教員養成と教員研修に関する研究を行った。スコットランドの学校体育では、子どもの体力、健康格差の是正と情意面の学習が重要な課題となっていた。教員養成では長期の教育実習による現場ベースの実践的な学びとキャンパスでの教授モデルを基にした学びを通した実践と理論の往還が特徴的であった。教員研修では、初年度の研修制度やオンラインプラットフォームによる研修記録の活用、研修情報の一元管理などが特徴的であった。
氏名 宮坂清
期間 2022年4月1日~2023年3月31日
国 日本
機関 琉球大学国際地域創造学部
研修課題 南西諸島のローカリティ形成における宗教の関与についての研究
研修概要
本研修は、期間前半は主に沖縄の宗教や民俗に関する文献調査を行い、期間後半は対象地域を八重山諸島に絞り現地調査を実施した。この現地調査においては、(1)石垣島の台湾人コミュニティ、(2)石垣島川平などの宗教民俗、(3)移住者たちのスピリチュアリティ、(4)与那国島の共同売店に関する調査を行い、八重山諸島に特有のローカリティの生成を観察することができた。今後も調査を継続したい。
学部 国際文化学部
氏名 佐伯奈津子
期間 2022年4月2日~2023年3月30日
国 インドネシア
機関 アルムスリム大学
研修課題 日系インドネシア人家族の軌跡
研修概要
太平洋戦争後もインドネシアに残留し、インドネシア独立戦争に参加した元日本軍兵士・軍属(残留日本人)が、インドネシア政治や日本との経済関係にどのような影響を与えたか、その家族がどのような暮らしを営んできたか、二世・三世への聞き取りや、互助組織「福祉友の会」での資料収集などを通じて調査した。
学部 スポーツ健康学部
氏名 四方田健二
期間 2022年9月1日~2023年8月4日
国 イギリス
機関 ストラスクライド大学
研修課題 イギリスの体育指導に関わる教員養成および現職教師の支援に関する調査
研修概要
研修中はDavid Kirk教授のもとでスコットランドの学校体育の実態および体育科の教員養成と教員研修に関する研究を行った。スコットランドの学校体育では、子どもの体力、健康格差の是正と情意面の学習が重要な課題となっていた。教員養成では長期の教育実習による現場ベースの実践的な学びとキャンパスでの教授モデルを基にした学びを通した実践と理論の往還が特徴的であった。教員研修では、初年度の研修制度やオンラインプラットフォームによる研修記録の活用、研修情報の一元管理などが特徴的であった。
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)
本学における「府省共通研究開発管理システム(e-Rad)」の管理は総合研究所事務室で行います。
原則として、専任教員(任期制含む。)として本学に雇用されている教員のみ、着任時にe-Radに登録され、それ以外の機会に登録されることはありません。
不明な点等に関しては、総合研究所事務室までお問い合わせください。
原則として、専任教員(任期制含む。)として本学に雇用されている教員のみ、着任時にe-Radに登録され、それ以外の機会に登録されることはありません。
不明な点等に関しては、総合研究所事務室までお問い合わせください。